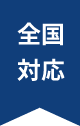障がい福祉事業の起業に興味のある方必読! 『 障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 』
こんにちは! 北日本ケアサポートスタッフ:Aです。
ここ数年、ニュースなどで「大人になってから、発達障害の診断を受けた」というような話をよく見聞きするようになりました。それに伴うようにして、障がい福祉事業所があちらこちらで開業しているように感じています。
これはおそらく、発達障害に対する認識が広がったことも要因の1つではないかと思いました。
そこで今回は、障がい福祉に関する基本的知識から障がい福祉事業指定の手続き、運営方法などが書かれた書籍『 障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 』をご紹介します。

・障がい福祉サービスと介護サービスの違い
この書籍の著者、行政書士の伊藤誠さんは多くの障がい福祉事業の指定申請などにかかわっており、その仕事の中で感じたことを巻末にこのような一文で書いています。
「(障がい福祉事業に関する)基本的な質問が非常に多い」
弊社北日本ケアサポートも、全国の障がい福祉事業所の国保連請求代行をしているので、なぜそのようなことになるのか、何となく想像がつきます。
書籍にも記載されていますが、障がい福祉事業は、指定権者の裁量や地域ごとのローカルルールが数多くあるため、一概に「このようなルールです」と断定できない部分があります。
そのため、開業を考えている地域のルールはどうなっているのか? 全国共通のルールとは? と混乱するのではないのでしょうか。
書籍を基に、障がい福祉と介護を比較した表を作成しました。まずは、障がい福祉サービスの全体的なイメージをつかんでみましょう。
*文章内の「障害」の表記は、厚労省または法令と同一にしています
| 障がい福祉(児童福祉を含む) | 介護 | |
| 根拠法 | 障害者総合支援法・児童福祉法 | 介護保険法 |
| 対象者 | 65歳未満の身体・知的・精神障がい者(児童も含む)・特定疾病患者*例外あり |
・第1号被保険者 ・第2号被保険者 |
| 利用料 | 決められた「上限管理額(*1)」までの範囲で自己負担 | 原則として、サービス利用料の1割を自己負担 |
| 財源 | 公費+利用者の自己負担額 | 公費+介護保険料+利用者の自己負担額 |
障がい福祉サービスも介護サービスと同様に、国保連(国民健康保険団体連合会)へサービスを提供した給付金の請求をします。
障がい福祉サービスの大きな特徴は、利用者の世帯所得区分に応じた「負担上限月額(*1)」が設定されていることです。
障がい福祉サービスの事業者は、この負担上限月額を超えた額を、利用者へは請求できません。この場合、上限を超えた額は国保連へ請求します。
*ちなみに介護では、要介護状態に応じて1カ月に利用できる限度額「区分支給限度額」があります。この限度額を超えた場合、介護では全額自己負担です
書籍では、この「負担上限月額」の仕組みにより、障がい福祉事業は未収リスクがきわめて少ないというメリットがあると書かれています。
*1:「負担上限月額」「上限管理額」については書籍に書かれており、今回は内容に触れません。北日本ケアサポートでは、あらためて詳細内容をお伝えしようと思っています

・障がい福祉サービスの種類
書籍にも書かれていますが、障がい福祉サービスは種類が多数あります。
しかも、利用対象者を障がい者にするのか、障がい児にするのかによって、提供できるサービスも異なります。
そこで、どのような障がい福祉サービスがあるのかをご紹介します。
《 訪問系サービス 》
ヘルパーや専門の資格を持ったヘルパーが、自宅へ訪問または外出に同行するサービス
| 居宅介護 対象:障がい者・障がい児 |
重度訪問介護 対象:障がい者 |
| 同行援護 対象:障がい者・障がい児 |
行動援護 |
| 重度障害者等包括支援 対象:障がい者・障がい児 |
《 日中活動系サービス 》
障害支援区分(*)がある障がい者・障がい児の日常を支援するサービス
| 短期入所 対象:障がい者・障がい児 |
療養介護 対象:障がい者 |
| 生活介護 対象:障がい者 |
*障害支援区分とは……障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもの(障害者総合支援法:第4条第4項より) 非該当から区分6まである
《 施設系サービス 》
施設に入所する障がい者を支援するサービス
| 施設入所支援 対象:障がい者 |
《 居住支援系サービス 》
施設とは異なり、地域での共同生活を支援するサービス
|
自立生活援助 |
共同生活援助(グループホーム) 対象:障がい者 |
《 訓練系・就労系サービス 》
自立した日常生活や社会活動ができるような訓練。または、就労に必要な訓練を行うサービス
| 自立訓練(機能訓練) 対象:障がい者 |
自立訓練(生活訓練) 対象:障がい者 |
| 就労移行支援 対象:障がい者 |
就労継続支援(A型) 対象:障がい者 |
| 就労継続支援(B型) 対象:障がい者 |
就労定着支援 対象:障がい者 |
《 障害児通所支援系サービス 》
集団生活への対応訓練などの支援サービス
| 児童発達支援 対象:未就学の障がい児 |
医療型児童発達支援 対象:未就学の障がい児 |
| 放課後等デイサービス 対象:就学年齢の障がい児 |
《 障害児訪問系サービス 》
障がい児の居宅を訪問し、発達支援を行う。または、保育所などを訪問し、集団生活への対応のための専門的な支援を行うサービス
| 居宅訪問型児童発達支援 対象:障がい児 |
保育所等訪問支援 対象:障がい児 |
《 障害児入所系サービス 》
施設に入所する障がい児を支援するサービス
| 福祉型障害児入所施設 対象:障がい児 |
医療型障害児入所施設 対象:障がい児 |
《 相談支援系サービス 》
利用者に対する利用計画の作成・モニタリング等を行うサービス
| 計画相談支援 対象:障がい者・障がい児 |
障害児相談支援 対象:障がい児 |
| 地域移行支援 対象:障がい者 |
地域定着支援 |
*障がい福祉サービスには、介護サービスのようなケアマネジャーがいない。そのため、ケアマネジャーと同等の役割を果たすのが相談支援系サービスとなる
いかがでしょうか? かなりの数のサービスがありますよね。
一つひとつのサービスについて、詳しくご説明したいところですが、今回は『 障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた 』の書籍にお任せしたいと思います(笑)
書籍では、障がい福祉事業を起業するうえで、上記のサービスの中から何を選ぶかを検討する必要があると書いてあります。その際に、各サービスを行った場合の給付金について試算し、毎日・毎月どのくらいの収益があるのかを確認する必要があるとのことです。

書籍ではこのほかにも、国保連へ請求するための給付金算定額の計算方法なども紹介されています。
私は介護事務管理士の資格を持っているので、障がい福祉の給付金の算定方法も理解できます。この辺りは、障がい福祉も介護の似た算定方法だと思いました。
書籍に載っている計算式は、以下のように書かれています。
| サービスごとに算定した単位数 × サービスごと・地域ごとに設定された1単位の単価数 = 介護事業所に支払われるサービス費(利用者は所得に応じた自己負担) |
パッと見ただけで、「何を言っているのかよく分からない……」と拒絶反応が出ませんか?💦
具体的な数字を入れて簡単に説明すると――
例) 札幌市の児童発達支援サービス(児童発達支援センター以外で行う場合で、定員10名以下)
| サービス内容(コード) | 児発15(611511) |
| 単位数 | 885単位 |
| 札幌市(七級地)単価 | 1単位10.18円 |
この条件で、1人の利用者が6日のサービスを受けた場合
885単位 × 6日 = 5,310単位
これに地域単価10.18円を乗算すると
5,310単位 × 10.18円 = 54,055円(端数切捨て)
この54,055円が国保連に請求する金額です。
*現在、児童発達支援等の利用者負担が無償化されています。対象サービスと対象年齢などの詳しい内容は厚生労働省のサイトへ→こちら
通常、各サービス事業所は基本報酬+加算or減算される項目が加わるので、上記のような簡単な計算にはなりません。
しかも、障がい福祉も介護も、3年ごとに報酬の改定が行われます。その際に、算定要件の変更などもあるため、その都度、自分たちが提供しているサービスがどのように変更されたのかを確認する必要があります。
ここまで読んで「障がい福祉の起業なんて無理だ……」と思った方、ちょっと待ってください!
この記事を書いている弊社、北日本ケアサポートは何を行っているか、ご存じでしょうか?
弊社は、皆さんが「無理だ……」と感じる障がい福祉や介護事業所のコンサルティングを行っています。
もちろん、障害福祉サービス等報酬の請求事務代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください♪
* 介護保険請求代行・障がい福祉サービス請求代行・事務代行料金 一覧
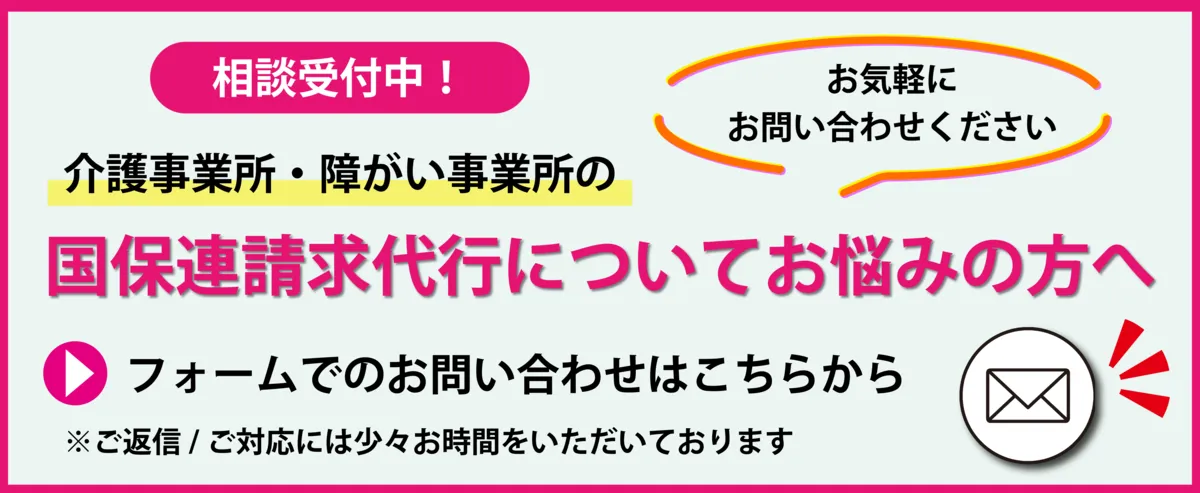 《 過去の関連記事 》
《 過去の関連記事 》
・介護事業所のコンサルティングとは? 具体的にどのようなことが頼める?
・就労継続支援事務所A型の給与計算 アウトソーシング・外注にするべき?
《 記事作成者 》 北日本ケアサポートスタッフ:A
北日本ケアサポートスタッフ:A
介護事務管理士 資格保持者
![介護保険請求代行、実績300事業所突破! 全国対応[北日本ケアサポート]](https://northjapan-caresupport.com/images/ci.png)